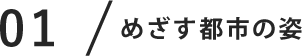
筑後川や耳納連山をはじめとした豊かな自然や、九州のクロスポイントとしての立地条件などに恵まれた久留米市は、これまで多彩な文化、多様な産業を興し、佐賀県東部を含む筑後平野の中核都市として発展してきました。
なかでも、4つの大学などの高等教育機関や試験研究機関といった学術研究機関の集積は、その高度な人的・知的資源や研究開発力を活かして、多様で質の高い教育環境のほか、産業界との有機的な連携による新たな産業の創出や、地域企業の高度化・構造転換などを生み出す、重要な地域資源の1つとなっています。
現在、我が国は本格的な人口減少・超高齢社会に入り、国際化・グローバル化の進展、分権型社会への転換など、地域社会を取り巻く環境は、大きく変化しています。このようななかで、久留米地域がこれからも将来に向けて自立的に発展する地域社会であり続けるには、地域全体の知的水準の向上を牽引する学術研究機関の役割が、いっそう重要となっています。
久留米学術研究都市づくりは、これまで培われてきた歴史、文化、産業、都市基盤等の蓄積を基礎に、産学官の連携強化等によって学術研究機能の更なる充実・強化を図り、「創造的な地域社会」の実現を目指すものです。


| 1983年(S58) |
|
| 1984年(S59) |
|
| 1987年(S62) |
|
| 1989年(H1) |
|
| 1992年(H4) |
|
| 1993年(H5) |
|
| 1994年(H6) |
|
| 1995年(H7) |
|
| 1996年(H8) |
|
| 1997年(H9) |
|
| 1998年(H10) |
|
| 1999年(H11) |
|
| 2000年(H12) |
|
| 2001年(H13) |
|
| 2002年(H14) |
|
| 2003年(H15) |
|
| 2004年(H16) |
|
| 2005年(H17) |
|
| 2006年(H18) |
|
| 2007年(H19) |
|
| 2008年(H20) |
|
| 2009年(H21) |
|
| 2010年(H22) |
|
| 2015年(H27) |
|
| 2017年(H29) |
|
「新・久留米市学術研究都市づくりプラン」![]() は、高等教育機関を取り巻く環境の変化や学術研究都市づくりの成果の蓄積を背景に、地域の産学官連携を一層推進するため、平成7年度に策定した「久留米学術研究都市づくりプラン」を見直したものです。
は、高等教育機関を取り巻く環境の変化や学術研究都市づくりの成果の蓄積を背景に、地域の産学官連携を一層推進するため、平成7年度に策定した「久留米学術研究都市づくりプラン」を見直したものです。
「新・久留米市学術研究都市づくりプラン」では、これまでの学術研究都市づくりの取り組みを継承し、「創造的な地域社会づくり」を基本テーマに、次のような都市づくりを推進します。

高等教育機関や試験研究機関等の多様な智の集積が連携し、地域とともに学び、高めあうことにより、新しい価値を創造し続けるとともに、自立した地域として継続的に発展し続けるまちづくりを目指します。
| 大学等との包括的な協定の拡充 |
| 地域と大学等との連携の促進 |
| 大学等と地域を結ぶコーディネート機能の充実 |
| 大学等が持つ施設の開放促進 |
| 学生の主体的な活動への支援 |

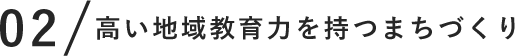
大学等の集積と連携を一層充実・強化し、高大連携等の地域の既存教育機関との連携強化や公開講座の充実等の社会や生涯教育の拡充等により、地域全体として高い教育力を持つまちづくりを進めます。
| 社会に期待される大学等づくり |
| 大学等間の連携促進 |
 |

| 地域の教育機関等との連携 |
| 国際的な人材の育成 |
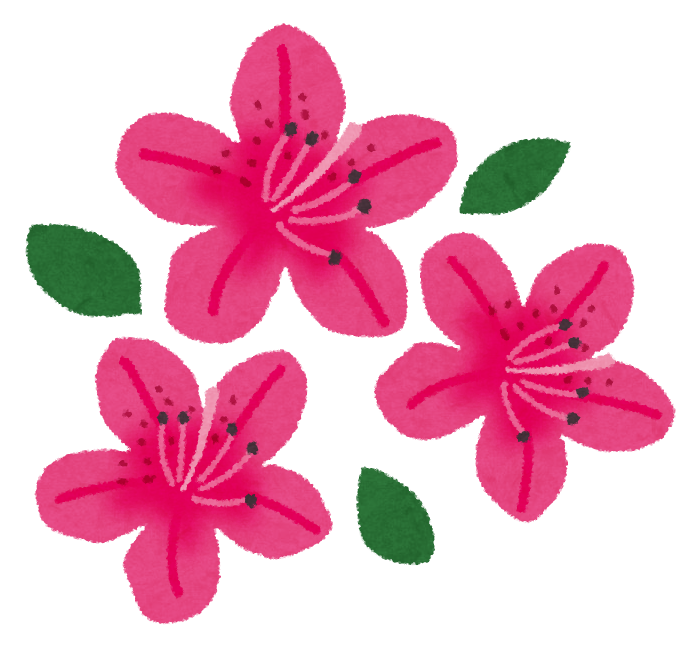 |

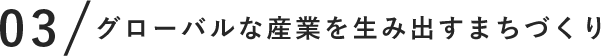
大学等の集積と連携を一層充実・強化し、高大連携等の地域の既存教育機関との連携強化や公開講座の充実等の社会や生涯教育の拡充等により、地域全体として高い教育力を持つまちづくりを進めます。
| ベンチャー創出支援の充実 |
| TLO機能の充実 |
| 国家プロジェクト等の積極的導入 |
| 知財センターの活用 |

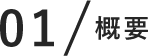
久留米学術研究都市づくり推進協議会は、久留米地域における学術研究機関等を充実・強化し、相互の有機的なネットワーク形成をすすめ、学術研究を中核とした都市づくりについて協議するとともに、九州北部における学術研究都市の拠点地域にふさわしい「久留米学術研究都市」の建設を推進することを目的に、平成5年7月に設立されました。
| 組織名 | 久留米学術研究都市づくり推進協議会 | |
| 事務局 | 住所 | 久留米市城南町15番地3(久留米市総合政策部総合政策課内) |
| TEL | 0942-30-9112 | |
| FAX | 0942-30-9703 | |
| 設立 | 1993(H5)年7月16日 | |
| 構成団体数 | 16(大学等4、公的研究機関等6、行政・経済団体・研究開発支援機関等6) | |
| 役員構成 | 会長 | 原口 新五(久留米市長) |
| 副会長 | 本村 康人(久留米商工会議所会頭) | |
| 内村 直尚(久留米大学学長) | ||
| 吉冨 巧(久留米市議会議長) | ||
| 会計監事 | 八尋 義文(久留米市農業協同組合代表理事組合長) | |
| 田中 達也(久留米リサーチ・パーク代表取締役社長) | ||

| 大学等 | 公的研究機関等 | 行政・経済団体・研究開発支援機関等 |
| 久留米大学 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター (久留米拠点) | 福岡県 |
| 久留米工業大学 | 久留米市 | |
| 久留米工業高等専門学校 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所九州センター | 久留米市教育委員会 |
| 聖マリア学院大学 | 国土交通省 九州地方整備局九州技術事務所 | 久留米商工会議所 |
| 福岡県工業技術センター | 久留米市農業協同組合 | |
| 福岡県農林業総合試験場 | 久留米リサーチパーク |

地域における学術研究の重要性の周知啓発及び産学官の連携・交流の促進を図るため、大学・試験研究機関等と連携し、科学技術の重要性や学術研究振興に資する事業の実施、後援等を行っています。
学術研究都市づくりに必要な各機関のネットワーク化や学術研究機関相互の連携強化等を図るために必要な事項について、調査研究を行っています。
学術研究都市づくり協議会のご案内や、協議会団体に所属している研究者データの公開などの活動を行っています。
| 教えて!ガッケン!! | |
| 第1回目(令和2年10月28日)放送分 | |
単位互換は、大学等が相互に単位互換協定を締結し、これらの大学に所属する学生が、他の大学等の授業科目を履修し、そこで修得した単位を所属する大学等の単位として認定しようとするものです。 単位互換協定に参加する大学等からは、それぞれ特色のある授業科目や、他の大学等には無いユニークな授業科目が提供され、学生の知的な関心や興味に応じた授業が行われます。 久留米市では、平成16年6月に、市内の5高等教育機関が「市内大学等単位互換に関する協定」を締結し、平成16年度後期から、単位互換制度を実施し、毎年200近くの講義が公開されています。また、平成17年度からは、「市内大学等単位互換に関する協定」に参加している5大学等が連携し、市中心部で一つのテーマに基づき講義を開設し、各大学等の講師がオムニバス形式で授業を行う「共同講義」も実施しています。
平成19年度より、“大学などの姿がみえるまちづくり”及び高等教育機関等の知の還元を通した地域貢献活動の具体化として、市内5大学等が連携・共同して、公開講座を実施しています。 毎回、統一したテーマを設け、地域の方々の生涯学習ニーズに応じた講座や、最先端の科学情報へのニーズに応じた講座、子供達に夢や、興味を与えるような講座など、各大学等の特色を活かした公開講座を実施していきます。











